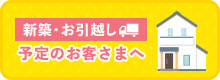2025年6月23日~2025年7月20日
- ホーム
- 2025年6月23日~2025年7月20日
2025年6月23日~2025年7月20日 若葉祭(うなごうじ祭)/つばめ桜まつり 第80回分水おいらん道中
若葉祭(うなごうじ祭):若葉祭(わかばさい)、通称うなごうじ祭。男衆がところかまわずごろごろと「うじ虫」のように寝ころがることで知られる、天下の奇祭です。
青年が駆け巡る祭りのクライマックスも必見!愛知県の無形民俗文化財に指定されている、伝統行事をぜひご覧ください。
つばめ桜まつり 第80回分水おいらん道中:今年で記念すべき第80回の節目を迎える「分水おいらん道中」。県内外の応募者から選ばれた「信濃」「分水」「桜」3人の「おいらん役」が絢爛豪華な衣装に身を包み今春も美しく咲き誇ります。「おいらん役」決定の瞬間から本番当日までの様子をぜひご覧ください。
2025年5月19日~2025年6月22日 左義長まつり/さわら雛めぐり
左義長まつり:湖国に春の訪れを告げる滋賀県近江八幡市の「左義長まつり」。左義長に飾り付けられる華やかな「ダシ」は、その年の干支を題材に、食材を使って作り上げられます。左義長を担いで練り歩く「渡御」や「組み合わせ」と呼ばれるダシ同士の激しいぶつかり合いのあと、五穀豊穣、疫病退散を願い奉納します。
さわら雛めぐり:かつて利根川水運で栄え、江戸の商家町の面影を残す千葉県香取市。毎年春には、各商家に代々受け継がれるお雛様が店頭に飾られ、華やかにまちを彩ります。祭りでは、7段飾りを模した7隻の舟に、煌びやかな雛衣装に身を包んだお内裏様とお雛様一行が、雅楽の美しい音色とともに小野川を舟で渡ります。
2025年4月21日~2025年5月18日 瀧山寺 鬼祭り/大曲の大綱引き
瀧山寺鬼祭り:鎌倉時代から800年続くと伝わる、天下泰平・五穀豊穣を願い、三河路に春を告げる天下の奇祭、瀧山寺鬼祭り。国の重要文化財に指定されている瀧山寺の本堂を舞台に祭りが行われます。祭りのクライマックス「火祭り」が見どころで、本堂が炎に包まれているような様子はまさに圧巻の一言です。ぜひご覧ください。
大曲の大綱引き:花火で有名な大曲で、約300年前から行われている小正月行事をお届けします。1匹の蛇とされる長さ136mの大綱に取り付けられた財振り棒は、回せば回すほど財を振りまくといわれ回す際に激しい攻防があり、この祭りの見どころの一つです。花火通り商店街で数百人が綱を引き合い、勝負の結果によってその年の作況が占われます。
2025年3月17日~2025年4月20日 師走祭り/大送神社綱引き神事
師走祭り:宮崎県の美郷町に伝わる「百済王伝説」。今から1300年以上前、朝鮮半島の古代国家・百済の王族親子が宮崎県に流れ着き、死後、父は美郷町南郷の神門神社に、長男は木城町の比木神社にそれぞれ祀られました。年に一度、親子が対面する祭りとして守り継がれている師走祭りをご紹介します。
大送神社綱引き神事:1月の寒空の下、地域住民が集い、力いっぱい綱を引きあう綱引き神事。これは、京都府南丹市八木町日置区、約60世帯の小さな集落で行われ、京都府無形民俗文化財に指定されている祭りです。北が勝つと麦や山のもの、南が勝つと米や里のものが豊作になると言われています。地域で受け継がれるお祭りをお楽しみください。
2025年2月17日~2025年3月16日 若宮稲荷神社 竹ン芸/鷲宮神社 強卵式
若宮稲荷神社 竹ン芸:10mもの長い竹の上で繰り広げられる迫力満点の狐たちの華麗な技。観客からは悲鳴とも感嘆ともとれる声が聞こえます。300年以上の歴史をもつ若宮稲荷神社の秋の大祭で奉納される「竹ン芸」。ここでしか見ることのできない狐たちの妙技をご覧あれ。
鷲宮神社 強卵式:鎌倉2代将軍・源頼家が幼少期「百日ぜき」を患うと、母・北条政子は鶏肉と卵を断ち鷲宮神社に病気平癒を祈願した…この故事にならい、咳止めの神様として地元で親しまれる栃木市の鷲宮神社では、秋の例大祭に「強卵式」を行う。山盛りの卵を食べろと責めたてる猿田彦にあらがう頂戴人とのユーモラスなやり取りが見どころ。
2025年1月20日~2025年2月16日 高岡神社秋季例大祭/大脇の梯子獅子
高岡神社秋季例大祭:高知県四万十町で行われる高岡神社の秋祭り。5つのやしろが並ぶ珍しい神社で、祭りは田畑の間を5基のみこしが巡行する姿が見ものです。今年は雨で巡行が中止となりましたが、祭りまでに行われる神職のみそぎや住民による準備の様子にレンズを向けました。四万十に息づく祈りと伝統を過去の映像を踏まえて紹介します。
大脇の梯子獅子:愛知県豊明市に伝わる伝統芸能『大脇の梯子獅子』。昼から夜まで数々の演目が披露されるなか、高さ10メートルを超えるやぐらの上で舞う獅子舞は圧巻!観る人の心を強く揺さぶります。五穀豊穣を願う神事として400年以上にわたり受け継がれてきた、地域にとってかけがえのない大切な神事です。
2024年12月23日~2025年1月19日 府招浮立/西条まつり
府招浮立:佐賀県伊万里市府招地区に400年以上伝わる伝統芸能「府招浮立(ふまねきふりゅう)」。
毎年10月第2日曜日の愛宕権現神社秋祭りに奉納されるこの祭りは、
太鼓や鉦の囃子に合わせて、華麗な衣装の踊り手が練り歩き、神を迎える「護神」などの演目を披露。
代々受け継がれてきた地域の宝を、ぜひご覧ください。
西条まつり:愛媛県・西条市内の中でも最大規模を誇る祭り・伊曽乃神社祭礼。
「だんじり」と呼ばれる屋台や「みこし」合わせて80台余りが市内を練り歩く豪華絢爛なお祭りです。
毎年10月15日午前2時頃から「宮出し」に始まり2日間、市内は幻想的な祭礼絵巻を再現します。
2024年11月18日~12月22日 目黒のさんま祭り/わらじ祭り
目黒のさんま祭り:古典落語「目黒のさんま」にちなんで、
炭火で焼いたさんまをふるまう、「目黒のさんま祭」。
目黒川から程近い会場で1500匹のさんまを豪快に焼く光景は圧巻!
また、めぐろパーシモンホールで行われた「第4回新作落語コンテスト」の様子もご紹介します。
毎年約3万人が来場する、都内の秋の風物詩をお楽しみください。
わらじ祭り:三重県志摩市大王町波切に伝わる「わらじ祭」。
村を荒らす巨人・ダンダラボッチを、村人たちが畳一枚ほどの大わらじをつくって見せ、怖がらせて退散させた、という言い伝えに由来しています。
300年以上の伝統を誇り、波切地区の人にとっては、小さい頃から馴染みのあるなくてはならないおまつりです。
2024年10月21日~11月17日 花火の里 ファンタジック福谷/鳥出神社の鯨船行事
花火の里 ファンタジック福谷:岡山市の福谷地区には県内唯一の花火製造所があり、「花火の里」と呼ばれます。
花火に特化した夏祭りには、地区内外から大勢が訪れます。汗を流して祭りを支える裏方たちの姿を取材しました。
鳥出神社の鯨船行事:鯨を大漁や豊穣の象徴として見立て、陸上で行われる模擬捕鯨行事は、三重県の北勢地域にのみ分布する民俗行事です。
鯨をさがすところから、攻防戦の末に仕留めるまでの一連のストーリーを、太鼓や唄にあわせて表現します。
豪華な船形の山車が激しく揺れる様子や人々の熱気、町が祭り一色に包まれます。
那智の扇祭り/ だいがく祭り
那智の扇祭り:熊野那智大社の例大祭「那智の扇祭り」は、国の重要無形民俗文化財に指定されています。
那智の大滝前の参道にて行われる「御火行事」は、
日本三大火祭りに数えられ、重さ50キロにもなる大松明の乱舞が見どころとなっています。
だいがく祭り:大阪府指定有形文化財である「だいがく」。
その高さ20メートルの迫力ある姿が披露されるお祭りです。
「だいがく担ぎ」行事では、音頭にあわせて中型のだいがくが2基、会場内を練り歩きます。
その内の一基は女性だけで担ぐ、「女性だいがく」。老若男女に愛されるだいがくの姿をお楽しみください。
-
お電話でのお問い合わせ
0120-993-138- 受付時間
- 9:00~18:00 年中無休
-
Webでのお問い合わせ